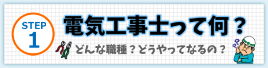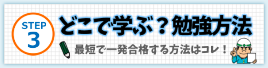本ページはプロモーションが含まれます
5つの失敗から学ぶ!電気工事士テキスト(参考書)の選び方
電気工事士の勉強をし始める際に、まず初めにテキストを買おうとして実際に本屋さんに行って、あまりのテキストの種類に、ビックリする人いませんか?私もその一人でした。
そこで、手当たり次第テキストを買って見づらい、分かりずらい・・・と何度無駄になったか分かりません!
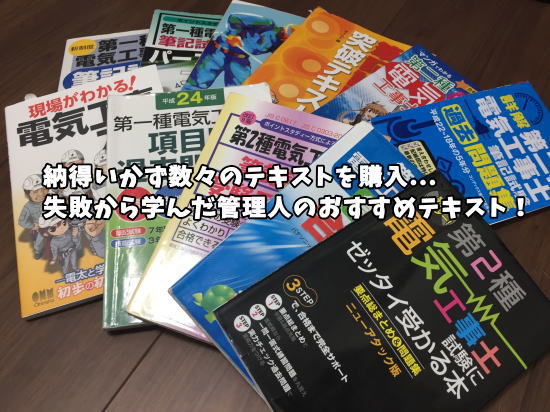
私が手にしたテキストは、数10冊。それらを見てきた経験からどのテキストがオススメか、どんな失敗があったかを紹介します。
失敗その① 詳しく書きすぎている
覚えなくても良い事まで書かれていると効率が悪い
私は本屋に行って、しっかり勉強するならこれ!とお勧めされていた本を初めに買いました。
まったく知識がない所から始めたので、これだ!と思い買ったのが失敗でした。いざ、中を開いて勉強を開始してみると、ページ1面に文字しか並んでいないです。また、1つ1つの単元の事が、ここまで書くの!?って所までびっしり書かれていました。
何かに例えると、漢字の読みを書くテストで、読みだけ覚えれば良いものを、【画数、書き順】までしっかり覚えさせられている感覚です。
つまり、勉強としてはしっかり役には立つが、テストにはまったく関係ない所まで覚えさせられるといった感じです。これにより、こんな覚えなきゃだめなのか・・・と挫折する人がいたり、まともに覚えようとして、勉強時間を大幅に増やさなければいけなくなってしまいます。
失敗の解決方法
詳しく書かれて過ぎている物は、初心者向けではないので、程よく絵なども使っていて、ここがこの単元では重要なポイントだよ?などの覚えるところがしっかり表記されているものを選ぶと良いでしょう。
失敗その② 絵が多すぎる
漫画だから分かりやすい、は誤り
読んで一番使えないと思ったテキストがこれです。
本の400ページぐらいある中の、半分以上がマンガで説明しており、初めて向けの人に読みやすく書いたつもりでしょうが、逆に良いとは呼べません。
まず、電気工事士の試験内容を強引にマンガにくっつけているので、説明が全然わかりません。ほんわか大事な所に触れているといった感じです。
また、マンガに出てたここの部分知りたいな?と思っても、知りたい事が出てこない事が多かったです。
結論として、こういう勉強があるんだな?として、参考にするぐらいなら良いとは思いますが、これだけで勉強をしようと思うのは絶対辞めた方が良いです。
失敗の解決方法
テキストがメインになっており、難しい所や、分かり辛い所を図や表で説明し、補足としてイラストを使い、吹き出しで説明してる物等が、勉強には向いています。
失敗その③ 工具の絵まで全てが白黒
フルカラーのものを選ばなければ苦労する
電気工事士試験では、写真を見て工具の使用用途と名前を答える問題が必ず出題されます。
そこで、工具の写真を見て勉強するのですが、その写真が全て白黒のテキストがあります。ただそこで問題なのが、実際の試験では工具の問題はカラーで出題されるのです。
例えば、電気工事士試験で一般的に使う圧着工具は、リングスリーブ用の圧着工具となっており、取っ手が黄色になってます。また、裸圧着端子用の圧着工具は取っ手が赤になっていて、色で区別出来るようになっています。
| 圧着工具 | カラー | 白黒 |
|---|---|---|
| リングスリーブ用圧着工具 |  |
 |
| 裸圧着端子用圧着工具 |  |
 |
上記の写真が圧着工具写真です。見比べていただいてどうでしょう?断然にカラーの方が分かりやすいですよね?また、頭の中では黄色がリングスリーブ用と思っていても、いざ試験になった時に何色だっけ?となってもおかしくありません。
失敗の解決方法
テキストを買う時は、事前に工具の写真がカラーで印刷されている物かを、確認してから買うようにしましょう。
本屋さんのお薦めだから、などではなく1度確実に開いて確認しましょう。
失敗その④ 重要度が分からない
出題傾向や重要度が記されているテキストを選ぼう
テキストで良くあるのが、この問題がどれぐらい試験にでて、どれぐらい大事な単元かを一切説明しないまま、全ての単元で練習問題が載っているテキストです。
実際にはどの単元も大事だとは思うのですが、まず試験を受けるのであれば、なにより合格を目指したいですよね?効率勉強するのであれば、出題傾向が高い問題を中心に覚えた方が絶対合格率は高くなります。
例として、下記のリストを見て頂くと分かりやすいです。
- 計算問題【様々な公式】 出題傾向5~10問
- 工具の鑑別の問題 出題傾向4~6問
- 配線図の問題 出題傾向約10問
上記の様に出題傾向が出ていれば、その単元がどれぐらい重要かが分かりやすいですよね?
また、勉強時間等の配分もしやすくなるので、勉強もスムーズにいきます。
失敗の解決方法
テキストを選ぶうえで出題傾向が書かれていたり、重要度が記されている物を選ぶようにすると、ここは大事なんだ!と意識して覚える様になります。
失敗その⑤ 練習問題が過去問と全然違う
実際に出題されない練習問題は時間の無駄!
ほとんどのテキストでは、1つの単元が終わる度に復習や確認の為に、練習問題などが多く出てる事があります。
大体のテキストではしっかり筆記試験に沿った問題が出ているのですが、電気工事筆記試験に全く出題された事の無い形式で問題が出ていたテキストもあります。学校のテストだったらあるとは思うのですが、電気工事士試験は国家試験なので無責任に大幅に問題形式を変える事は無いです。
実際テキストであった、こんな問題出ないですけど・・・。という問題は文章の漢字での穴埋め問題でした。
例 ガラスやプラスチック等の電気を通しにくい物を()といいます
これを漢字で書きましょう。の様な感じです。
ここで、筆記試験は4択のマークシート形式です。絶対記入式の問題は出る事がありません!また過去問+基礎を覚える為に、上記の様な穴埋めなら分かりますが、穴埋め問題の様な試験に出る筈の無い問題ばかりのテキストもあります。
失敗の解決方法
テキストの問題欄を確認し、穴埋めや自分で記入式の問題が多い場合は注意しましょう。
筆記試験を想定して作っているテキストは、必ずイロハ二の4択の筆記試験と同様の、選択式の問題になっています。また、電気工事士試験の過去問をそのまま載せているテキストもあるので、そちらであれば間違いないと言えるでしょう。
各社電気工事士資格のテキスト【参考書】比較
第二種電気工事士のテキストは、数多くの出版社から出ています。その中でもどの出版社がどの様なテキストで、どの様な特徴があるかを、下記の表に分かりやすくまとめました。
4社を比較・筆記用参考書(オーム社・電気書院・ツールボックス・土屋書店)
2019年1月調べ。
3社を比較・技能用参考書(オーム社・ツールボックス・日本電気協会)
2019年1月調べ。
各社筆記試験・技能試験の参考書を載せましたが、やはりどのテキストもメリットは有り、デメリットもあります。参考書だけでは全てを補うには難しいのかもしれません。
私が学んだ電気工事士のオススメ勉強方法(テキスト・参考書)
初心者は絶対コレがおすすめ。DVD付きで易しく確実に学べる
ここまでで、私自身が学んだ10数冊以上のテキストの情報をまとめましたが、やはりどの参考書もメリット・デメリット大きく分かれていました。
私が使った中で一番良いと感じたのがユーキャンのテキストです。なぜ沢山の参考書を見てきた私が、ユーキャンのテキストがオススメだと言うかは下記の3つの理由からなります。
①時間配分や重要点が示されている
他の参考書は何カ月で勉強が出来る等の大雑把な時間配分の説明だったが、ユーキャンのテキストは単元毎に、ここは何日以内で覚えてください等、しっかり難易度に合わせて時間配分が決められています。
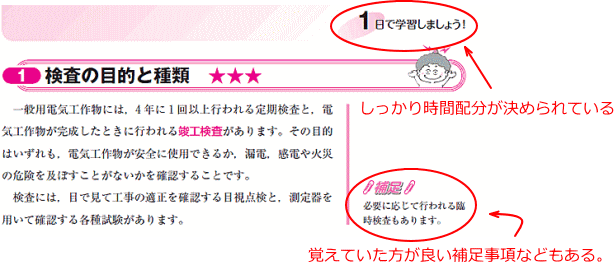
それにより、どんな初心者の方でも安心してテキストにそって、勉強が出来るので時間に追われて、試験前に焦って勉強する事がなく安心できます。
更に、重要点などがしっかり記載されているので、私の場合試験1週間ぐらい前から復習としても利用できたので、大変助かりました。
②フルカラーで、名前や使用用途も全て無駄な言葉を無くし記載されている
他の教材、参考書、等では写真は白黒だったり、文字だけの参考書もありましたが、ユーキャンのテキストでは、写真がフルカラーになっている。
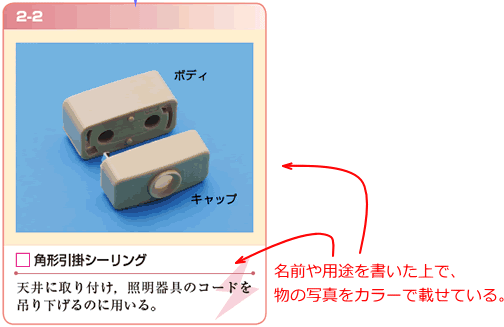
上記の様にフルカラーで、写真のすぐ下に名前や使用用途が書かれているので、覚えやすい!
③文章でのテキスト以外にもDVD等動画のテキストでも学べる
実際これがかなり大きいです(笑)。参考書だけではどうしても写真や文書のみなので、どうやってそこの作業したんだ?等の疑問が多く生まれ悩んだ事が多くありました。
ユーキャンはDVD等の動画式のテキストもあるため、技能試験を映像で覚える事が出来ます。これが試験の際に大変役立ったことを覚えています。
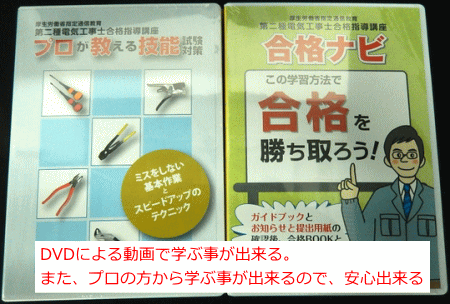
技能試験は参考書だけで勉強はどうしても無理でした。また、仮に参考書で覚え、作業自体は出来ても、時間が足りずダメだったり・・・、そんな時にこのDVDのテキストを見ると、コツ等がしっかり書かれていたので時間短縮にも繋がりました!
ユーキャンのテキストは他の参考書に比べデメリットがないので、やる気さえあればどんな初心者の方でも分かりやすく学べるのがメリットです。
- ユーキャンの電気工事士講座について詳しくはこちら→ユーキャン
電気工事士講座はユーキャンがおすすめ!無料で資料請求できます
☆ユーキャンのいいところ
・勉強に必要な教材・練習用材料が揃っている
・技術試験対策のDVDが付いている
・スマホから視聴できる動画やWebテストがありスキマ時間が活用できる
10年間の合格者は5,800人を突破していて、初学者が90%なのではじめてでも安心。