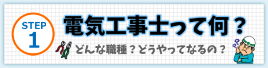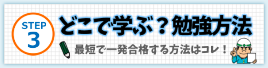本ページはプロモーションが含まれます
数学が苦手でも電気工事士試験に合格できる!3つのポイント
この3つのポイントを抑えれば合格率がアップします!
電気工事士を目指しているけど、全く数学の知識がないからどうしよう!と思っているあなたに、このページでは【電気工事士試験で使う数学】に関する合格する為の3つのポイントを解説しています。
- ポイント1.電気工事士に必要な数学の基礎って何??
- ポイント2.電気工事士試験に出てくる数学の問題を見てみよう
- ポイント3.数学が苦手な人でも電気工事士試験に合格できる!
ポイント1.電気工事士に必要な数学の基礎って何??
3つの基礎を覚えるべし!
電気工事士では下記の数学の知識が必要になってきます。詳しく見ていきましょう。
- 基礎1.分数
- 基礎2.オームの法則
- 基礎3.合成抵抗
電気工事士の数学の基礎1.分数
まず基礎として分数は絶対覚えてください。
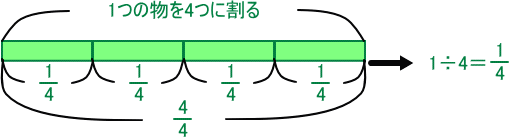
こう見ていただくと分数は難しくないですよね?また、分数を使った計算を覚えてみましょう。
分数の足し算のやり方
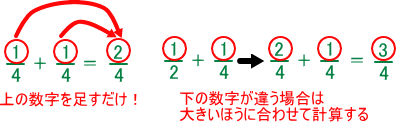
※上の数字は分子、下の数字は分母と言います。小学校で習ったこういう基本の計算って意外と忘れてしまっていますよね^^;
足し算のやり方はとても簡単で、分母が同じ場合は分子を足すだけで、分母が違う場合は分母を合わせて計算をする、ということを思い出しておきましょう。また、注意点として分母を合わせた場合に分子も合わせて同じ数字を掛けるのを忘れないようにします。
分数の掛け算のやり方
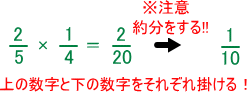
分数の掛け算は分子と分母をそれぞれ掛け算するだけ。ここで忘れてはいけない注意点が、約分です。
ちょっと昔を思い出してみましょう。約分とは、分母と分子がそれぞれ同じ数字で割り切れる場合、分数を小さい数字にして簡単にすることでしたよね。
約分をしないと電気工事士試験の際、答えが合わない場合があるので注意しましょう。
分数の割り算のやり方
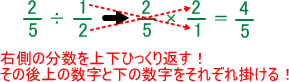
分数の割り算も試験で使用します。分数の割り算のキホンは、「ひっくり返して掛ける」でしたね。割り算の右側の分数を上下逆にし後は掛け算するだけなので、難しくありません。
電気工事士の数学の基礎2.オームの法則
分数の次に重要になるのがオームの法則です。
オームの法則は電気工事士のほぼ全ての数学の問題に関わっていると言えます。
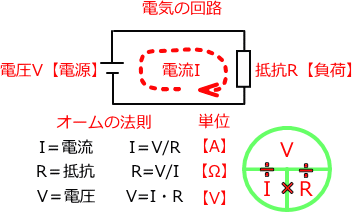
中学生の理科の授業で勉強するので、見たことがある!と思いだした方も多いと思います。
オームの法則は電気工事士の資格試験で確実に使うものなので、図の電流(A)、抵抗(R)、電圧(V)の関係は確実に覚えなければいけません。
- オームの法則の詳しい解説はこちら→資格取得の勉強を体験してみよう!
電気工事士の数学の基礎3.合成抵抗
3つ目の電気工事士の数学の基礎として重要になるのが合成抵抗です。
合成抵抗とは、2つ以上の抵抗を1つの抵抗として考え、値を1つにまとめる事です。
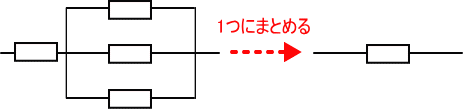
合成抵抗には二つの種類があります。
- ①直列接続又は直列回路
- ②並列接続又は並列回路
どのような接続なのかを詳しく見ていきましょう。
①直列接続・回路
![]()
上記の図や名前の通り、直列回路とは回路が分かれることなく1本の道としてつながっている回路のことです。
直列回路の合成抵抗を求める方法はとても簡単で、全ての抵抗の値を足していくのみとなっています。では1つ例を見てみましょう。
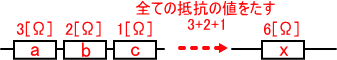
上記の様に直列接続の合成抵抗はとても簡単に求めることが出来ます。
②並列接続・回路
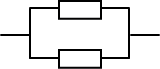
並列回路とは、回路が2つ以上の道に別れつながっている回路のことです。
並列回路の合成抵抗を求める方法は2つあります。
- 和分の積
- 並列接続の際の合成抵抗の公式
和分の積を計算する場合、抵抗は2つでないと計算する事が出来ません。
しかしそれとは違い並列接続の際に合成抵抗の公式を使った場合は、3つ以上の抵抗があったとしても、一度の計算で合成抵抗を求めることが出来ます。
ではそれぞれの例を見てみましょう。
和分の積
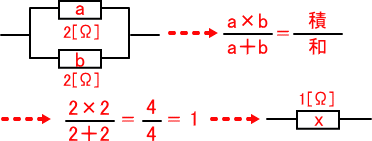
また3つ以上の場合でも下記の様に求める事も可能です。
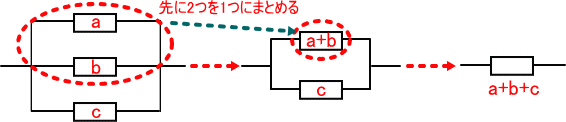
並列接続の際の合成抵抗の公式
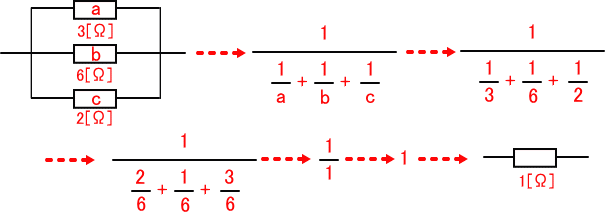
このようにそれぞれ並列接続の場合2つのやり方があるので、自分のやりやすい方で計算しましょう。
ポイント2.電気工事士試験に出てくる数学の問題を見てみよう!
ポイント1.を覚えれば問題の内容は応用だけ!
ポイント2ではどの様な数学の問題が試験に出てくるかを確認し、やり方を覚えて少しでも苦手意識をなくしてみましょう。
平成26年上期の合成抵抗の問題
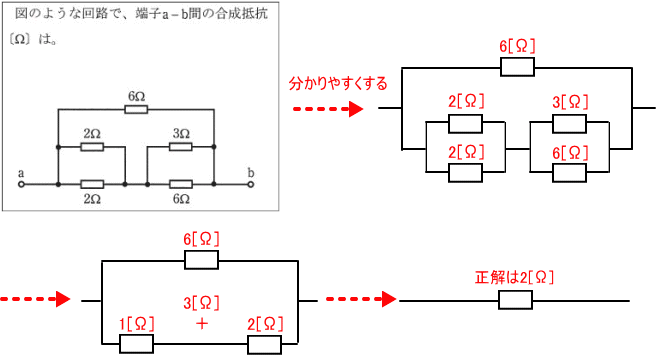
上記の合成抵抗の問題ですが、初めて見ると少し難しく感じてしまうかもしれません。
しかし、ポイント1で解説している合成抵抗のやり方さえ知っていれば、落ち着いてゆっくり1つ1つやることで確実に解く事が出来る問題です。
平成23年下期のインピーダンスを使った問題
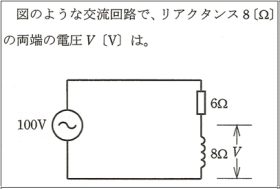
これはインピーダンスを使った問題になりますが、公式さえ覚えれば難しいことはありません。インピーダンスとは抵抗の他に、リアクタンス(コイルやコンデンサ)がはいった回路の合成抵抗の呼び方です。
コイルは電圧をあげたり下げたり・電気と磁気を互いに作用させて色々な働きをさせたりするのに使い、コンデンサは電気を溜め込んで排出する電池の役わりをしたり、直流の電気を流さないようにしたりするどちらも皆さんの周りに多く使われているものです。
基本はオームの法則を使いますが、リアクタンスが入った場合の合成抵抗の求め方が変わるのでそこに注意して問題を見てみましょう。
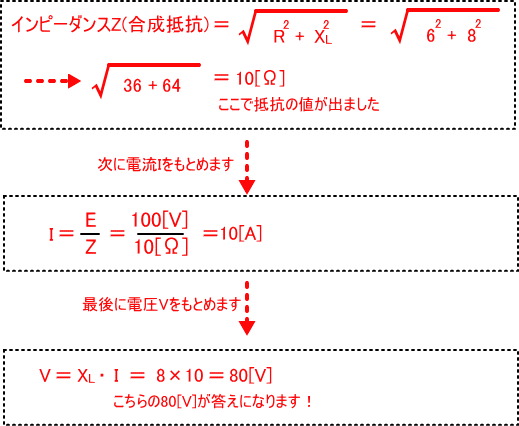
やっていること自体はとても簡単な式になりますが、問題を解くまでの課程が長い問題です。パッと見は難しく見えますが、何にどの公式を使うかを間違えなければ問題ないです。
- 他にもどんな過去問があるかを確認したい場合はこちら→電気技術者センターの公式HP
ポイント3.数学が苦手な人でも電気工事士試験に合格できる!
数学が一切出来なくても他の問題が解ければ合格することが出来る!
ポイント1.ポイント2.を見たけれど、どうしても数学が苦手で分からない・・・
安心してください、そんなあなたでも電気工事士試験に合格することは可能です!電気工事士試験には、毎年問題の出題傾向が存在するからです。
| 出題傾向 | 問題数 | 配点 |
|---|---|---|
| 計算問題 | 5~10問 | 10~20点 |
| 暗記問題 | 20~25問 | 40~50点 |
| 配線図 | 20問 | 40点 |
| 合計 | 50問 | 100点 |
上記の表を見て気づいた方もいるかと思いますが、何と全体に対しての計算問題の割合は5~10%ほどしかありません。
第二種電気工事士の試験の合格点は60点以上と決められていて、どうしても計算が苦手な場合でも暗記問題と配線図の問題で試験に合格することも可能ということになります。
ただ、やはり余裕を持って合格する為には計算問題も完璧にする必要があります。その場合どうしても、独学で数学を勉強するのは厳しい部分が出てきます。
電気工事士試験対策のための数学の学習方法
実は私自身もものすごく数学が苦手で、テキストを買い漁って勉強しようとしたのですが難しく、結局ユーキャンの電気工事士講座で学び一発合格しました。
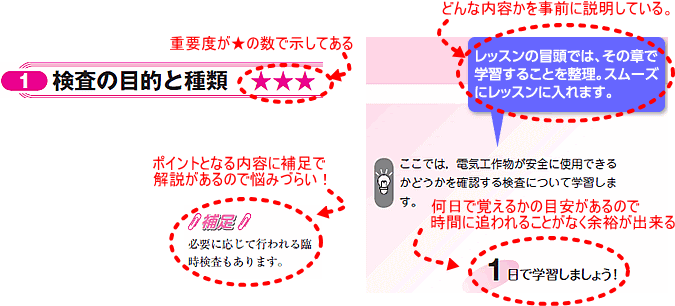
ユーキャンは悩んだ際にすぐに質問ができる環境があり、重要度が示してあったり補足、解説、何日で覚えるかの目安もあり勉強方法にさまざまな工夫がされていて、最終的にこれのみで合格することができました。
それまでに購入したテキスト・参考書は結局最終的には使いませんでした^^;
- ユーキャンの電気工事士講座についてはこちらに詳しく書きました→ユーキャン
電気工事士講座はユーキャンがおすすめ!無料で資料請求できます
☆ユーキャンのいいところ
・勉強に必要な教材・練習用材料が揃っている
・技術試験対策のDVDが付いている
・スマホから視聴できる動画やWebテストがありスキマ時間が活用できる
10年間の合格者は5,800人を突破していて、初学者が90%なのではじめてでも安心。